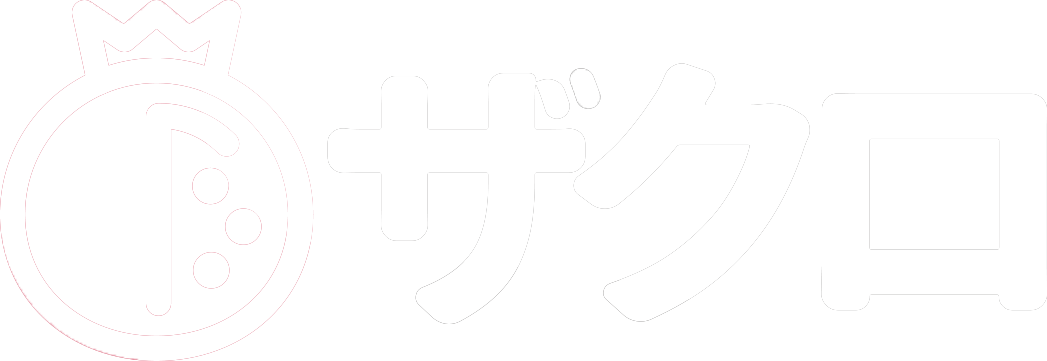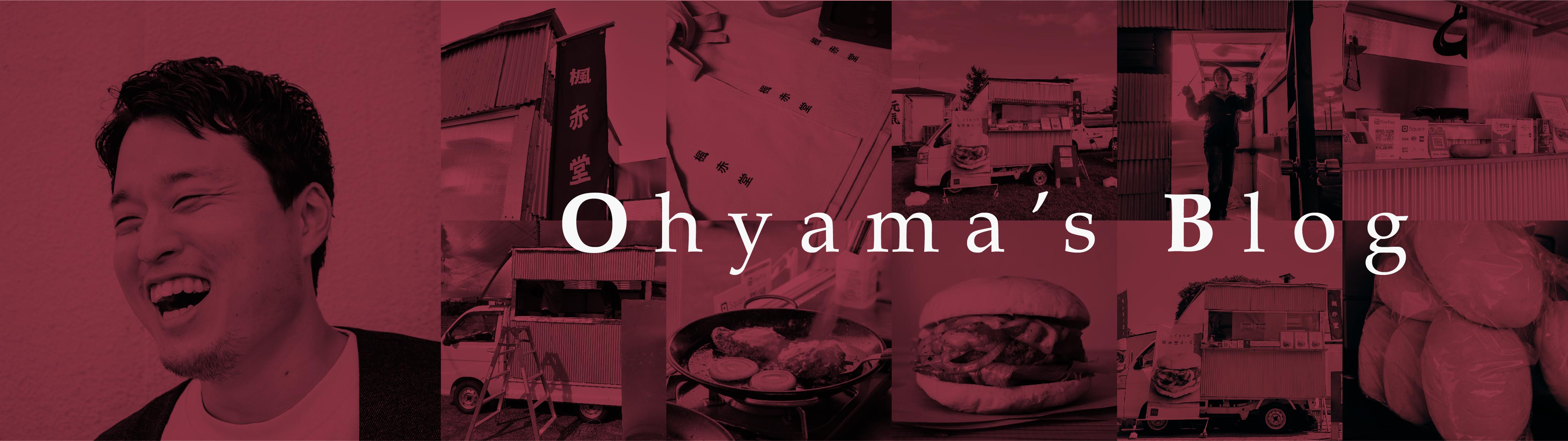2023/05/28 Sun
FUSEKIDO Ohyama wrote
489 Views
<キッチンカー運営を決断するまでの過程> ~学生時代の経験によるマインドセットの醸成編_2~全く0の状態からなにかしらの成果が得られるまでの経験は、高校時代の球技祭や、文化祭しかり、大学時代の研究もそのひとつだろう。 大学での研究というのは、主に大学の先生が研究テーマを持っており、そのテーマに沿って、ドクターやマスター、学部生が研究活動を行う。 研究のテーマというのは細分化されている。既存の研究を読み込むことでそのテーマの潮流を読み解いて、異なるアプローチや、懸念点とされている部分の改善案を提案することが研究活動である。そのため、研究室に配属された新人はまず、3か月弱程かけて、既存研究を読み込み、自身はどんな改善策を提案するのかの構成を練っていく。
この既存研究や、自身が考えた手法によって、学部生であれば20代前半の若手であっても、狭い分野でありながら、その分野の第一人者であり、さらに自身の提案が学会に評価されると、研究の楽しさを感じるものである。
私の大学院での研究生活と言えば、先生が大学に赴任したばかりで、新設研究室であった。初年度は3人の修士課程と、2人の学部生。研究室内は前の研究室が残していったガラクタにまみれ、ラボの掃除から始まった。
研究テーマはGPUの並列計算を使用した機械制御アルゴリズムの研究で、GPUを使用するためのC言語ベースのプログラミング技術の習得と、制御プログラムの検証として、倒立振子を使用した実機への適用。最終的には海外学会への参加までさせてもらい(ポスター発表だが、、)、大学院2年間は研究室立ち上げから、成果を出すまで経験できた。
学術の世界はとても広く、私なんかが一つの成果を上げただなんて、とても恐れ多くて言えないのだが、大学院での研究活動は、高校生活から続いて全く0の状態から何かを作り上げて、人に評価してもらえることの「学生・研究者として」の集大成ではあったのではないかと考える。
しかし研究活動というのは、基礎研究であり、すぐに人の役に立つものは多くない。こうした基礎研究は技術の根幹であり、今後の技術革新への足がかりとなっていくものであり、研究者への投資は将来への技術優位性を保つための投資であるが、現在の日本では大学で研究をしながらお金をもらえる仕組みではない。
このままマスターからドクターに進学した先にどんなキャリアがあるのかが見通せなかったことと、大規模な生産と雇用を創出する企業活動というものに興味を持っており、修了後は就職を選んだ。